|
ブランデンブルク協奏曲の新盤に寄せて
――オリジナル楽器によるバッハの演奏――
(「季刊GRC」第9号[1978年3月発行]所収)
(5)
■このレコードの特徴――結び
オリジナル楽器によるバロック音楽の演奏がここまで盛んになって来ると、それに伴っていろいろな弊害も出て来る。
レオンハルトやブリュッヘンは、当人達の意志とは全く無関係に、新しい権威の座に祭り上げられ、数多くの模倣者が続出する。「十九世紀」を極度に忌避するアンバランスなバロック楽器奏者の卵達は、十九世紀の音楽や楽器をも無条件に拒絶する。彼等の御題目は常に「正統性」であり、レオンハルト、ブリュッヘン、ヴィーラント・クイケンらの演奏は格別に「神聖化」される――いや、極言すれば「神格化」される。
こうなると宗教になる。「オリジナル教」の出現である。
オランダでは、今でこそ、こうした話にならない妄信者はだいぶ減ったが、2、3年前は、ハーグ王立音楽院などは「オリジナル教」信者の巣窟であった。現在でも、世界中にこの種の狂信者はたくさんいるのであろう。
オランダで活躍しているバロック演奏の巨匠達は、この風潮にはかなり頭を痛めており、ベイルスマなどは、「ロマン派音楽だろうが、バロックだろうが、人間の感情に訴えることにどんな違いがあるものか!」と、強調していた。
レオンハルトは、この新しいブランデンブルク協奏曲のレコード解説の中に、「オリジナル楽器による演奏について」という一文を書いている。この文章は、現在の「オリジナル楽器によるバロック演奏」を取り巻く様々な状況について配慮し、一方では前述のような狂信者に対して、もう一方ではこうした新案に全く不慣れな人達のためにも書かれており、レオンハルトの「演奏に対する理念」なども現われていて、彼の考えを知る上では極めて興味深い手掛りとなっている。
《説得力があれば、その人の演奏したものは正統的な印象を与える。自分で正統的たらんとすれば決して説得力を持ったものにはならない。》と、先ず彼は警告する。《正統対非正統――これとて、一体誰に判定出来よう! 私は、この録音が「決定的」なものとか「正統的」なものとして折紙付きにならないよう願っている。》
本来、音楽作品の演奏について、ある特定の演奏のみが決定的なものであるということはあり得ない。また、そんな捉え方で、音楽というものは決して楽しめるものではないのである。しかし、彼はこの言葉によって「正統性への探求」を放棄したわけではない。彼の演奏態度の底にあるものは次の言葉に要約されている。《ある偉大な精神とその時代の持つ思考の世界の内に没入しようとする演奏家だけが・・….真なるものと純正なるものを呈示しているという感銘を呼びさまし得るのである。》その故に、彼は《歴史的な研究の重要性を認め、それを自分の仕事の一部であると考えている》わけであり、彼の関心は所謂表面的な「正統性」より遥かに深い所にあるのであって、「博物館趣味」だの「考古学的探究」とは緑がない。《正統性などよりも私にとって重要なのは、もっと言葉では捉えにくい問題である。》それは、応々にして、理性などでは捉えられない問題、《心の》問題であり、それはとりも直さず、《芸術》の本質に関わる問題なのである。
そして、このレコードの演奏については、次の言葉によって、実に控え目ながら、その特徴を実に的確に言い表わしている。
《この録音は、歴史的な研究の重要性を認め、それを自分達の仕事の一部だと考えている音楽家達が、これを「特殊な」ものとして感じることもなく、ましてそれを目立たせることもなしに演奏したものである。》
このレコードの演奏は、レオンハルト独りの個性によって支配されているわけではない。この録音に参加している一人一人の奏者が、楽器の奏法から演奏解釈に至るまで、長い間求め続け、考え抜いたもの――バッハを、彼の時代を内側から感じるために数々の試行錯誤をし、彼等一人一人が自らの内面的な要求に基づいて自分自身で把みとったものが随所に息づいているのである。筆者がこの文の初めで述べた、「各人が積極的に音楽に参加している」とは、正にこの意味に於てである。このようなレコードを作ることは、十年前はおろか、五年前でも恐らく不可能であったろう。オランダに於る、オリジナル楽器演奏の歴史二十年の成果がここにある。その意味で、このレコードは単に名盤というのみならず、数あるこのシリーズのレコードの中でも特筆に価する画期的なものと言わねばならない。
この録音に参加した奏者達は、皆個性の強いソリストばかりである。その奏者達を、その一人一人の個性を超えて一つのものにまとめあげたレオンハルトの才能と実力は誠に驚嘆すべきものである。
様々な斬新さが、このレコードを一層楽しいものにしている。各曲毎に詳説している紙数の余裕はもう無いが、例えば、第一番の終楽章のメヌエット。ここでレオンハルトは全く新しい解釈を行なっている。
第3番と第6番の、オリジナル楽器ならではの響きの魅力、それに加えて、聴いていて知らないうちに身体が思わず動いて来てしまう、この強烈なリズムとダイナミズムは、レオンハルト独特の持ち味である。
そして第5番。ここで一番物を言っているのは、オリジナル楽器を使わねば到底得られない各楽器間のバランスである。この曲は、完全にチェンバロ奏者の独壇場である筈なのだが、通常の楽器で演奏すると、独奏ヴァィオリンとフルートによって、チェンバロ・パートの細かい動きが全く聴こえなくなってしまう。例えば、第1楽章のかなりの部分で、チェンバロの右手には、バッハの他のチェンバロ音楽の書法に比べると、かなりアグレッシヴな和音の連続があって、それがヴァイオリンとフルートの奏する緩やかな旋律線と好対照を為すように書かれているのだが、それがこんなに見事にくっきりと表現された演奏は他に例を見ない。とは言うものの、ブリュッヘンのフルートがもう少し音量を押えてくれれば、と思うような箇所もところどころにあるのだが――
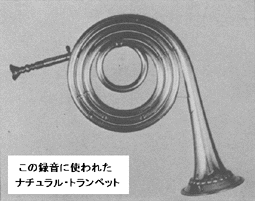
ただ、第2番のみには不満が残る。トランペット奏者の技術の不足が目立ち過ぎるのである。この時代の楽器はピストン等のメカニズムを全く持たない1本の管で、ただ奏者の唇の操作のみで音程を作らなくてはならないという、とんでもなく難しいものであることは確かで、4本もピストンを持つ現代のピッコロ・トランペットと比べることに意味が無いのは解ってはいても、そんな弁解を何遍繰り返したところで、モーリス・アンドレの超人的な名人芸に慣れた現代人の耳を満足させはしないだろう。もう少し上手なトランペット奏者を見つけることは出来なかったのだろうかと、それだけが残念ではある。
ともあれ、バロック楽器の響きの多様さが、この曲集に於るバッハの驚嘆すべき楽器法と相俟って、こんなに魅力的なものとなっている演奏は少ない。このような色彩感は、通常の楽器には求め得ないものである。
レオンハルトは、その文中で、楽器の響きの特質について、次のように列記している。《様々な楽器の間のバランスが今や全く自然になっていること、後の楽器の平坦さに比べると、ここでは、豊かさが音の陰影の多様さと木管楽器の音高の繊細さで表われていること、また、ここでの弦楽器が、他の音楽には適している後の時代のものに比べると、もっとやせてはいながら、もっと内容のある響きの組立てを持っていること……》
この説明を読んで、後の時代の楽器よりバロック期のそれが優れていると受け取る必要はない。先にも述べたが、それらは単に違うだけである。ロマン派音楽のニュアンスのつけ方はバロック音楽のニュアンスのつけ方とは違うし、ロマン派の楽器のニュアンスはバロック楽器のニュアンスと異なる。《それぞれの時代には、その時代の音楽にふさわしい楽器があったのである》(ニコラウス・アルノンクール)。そして、適材が適所に使われれば、その方がよい結果を生むのは当然である。
と言っても、初めてバロック楽器を聴く人はその耳慣れない響きに当惑するかも知れない。しかし、だんだんそれに慣れて行けば、その人はやがてその新しい響きを楽しんでいる自分を発見するにちがいない。その時には、その新しい響き・新しい演奏のつきつけているのっぴきならぬものを体感しているにちがいないのだ。人間だって、文化だって、その内容を理解するためには、多少のつきあいは必要であろう。そこへ恐れずに跳び込んで行きさえすれば、その時その時のつきあいを楽しむことが出来る筈だと思う。
勢いに委せて、つい長々とここまで書いて来てしまった。ブランデンブルク協奏曲の新しいレコードを聴くために、こんなに沢山の予備知識が必要なわけでは毛頭ない。しかし、こうした新しい響き、新しいタイプの演奏に不慣れな方々も少なくなかろうと思い、僭越ながら道案内の役を自らつとめた積もりではある。別に大して必要のないガイド役だったかも知れないが、より早く、より容易にこうした演奏を楽しんで頂きたいと思い、かえって説明が細かい専門的な事柄に深入りし過ぎたのではないかと案じている。
音楽というものは、要は楽しめればよいのである。純粋に楽しんで頂ければ何も言うことはないのだ。そして優れた芸術作品は、それが優れていればいるほど、多様な楽しみ方が可能な筈である。
最後に、レオンハルトの文の最後の部分を引用して結びにかえたい。
《耳は、ひとが思い勝ちなよりも早く慣れるものであり、それで良いのである。そうすれば、楽器は演奏者と聴き手にとって、再び、文字通り音楽に仕える「道具」になるのであり、全ての専門家や愛好家達は、絶えず新たに驚嘆しながら、ヨハン・セバスティアン・バッハの中庸に対する確かな感覚と測り知れない独創力に夢中になってしまうことが出来るのである。》
(1)│(2)│(3)│(4)│(5)
渡邊順生著作一覧へ
ページのトップへ
|